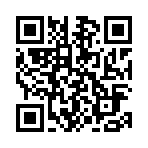2010年11月10日
携帯用日時計

木製のケースに収まった、携帯用の日時計。

真鍮のリングとプレートを立ててセッティングする。
糸と重りを使った、簡単な水平器まで付いている。
内蔵(?)の方位磁石に合わせて真北に向けて置くのがポイント。
プレートによる影で時刻を読む。

蓋の内側には、明石の標準時とのズレが都道府県ごとに記されている。
これでおよその時刻が計算できるというものなのである。
真昼間のしかも晴天でしか使えないのが難点だが、自然から時刻を読めるなんて
夢があって素敵じゃないか。
今のように一分一秒を争うような時代でなかった頃。
懐からおもむろにこれを取り出し、しばしセッティングの後、計測し、
「ああ、もう正午になるねえ」
「そうかね、めしにするかい」
てな具合に会話がされていたのだろうか。
恐らく江戸後期から使われ、
同型の復刻版は、明治、大正から戦前くらいまでは作られていたようだ。
これ自体がいつ頃のものかは不明である。
資料的な意味だけでなく、こういう夢のあるものには心惹かれる。

タグ :携帯用日時計