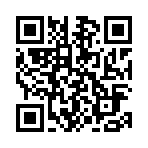2014年10月25日
古い革の風合い
ちょっとやそっとでは醸し出せないこの風合い。
自分の人生がこの風合いを出せるまで、まだまだ、まだまだ、なのである。
新しいブログはこちら
http://travelersmind.cocolog-nifty.com/blog/
2014年06月07日
精工舎のトラベルクロック
グリーンのお洒落な革ケース。
チャックを開けると、これは懐かしいトラベルクロックである。
よくある樹脂製のパコって開く物と違って、革ケースでファスナーを使ったものはあまり見ない。
やっぱ、革はいい。
精工舎製である。
文字盤のデザインもいいなあ。
表面はガラスではなく、旅行用らしく割れにくいセルロイド製である。
裏側も懐かしい。
ムーブメントの発条とアラームの発条。
そして、速度調整の目盛ももちろんついている。
これによって、結構正確に時を刻む。
やはり同じ精工舎のちょっと古い“へそ目”に仲間ができた。
今度の夏の旅には連れて行こう。
2014年06月04日
折りたたみイス用革ケース
革でケースを作った。
今回初めて、ジャンパーホックを使ってみた。
1回使ってみると、これは便利だ。
裏側にはベルト通しも。
さて、これ何のケースかというと・・・。
先日menuで譲っていただいた、この折りたたみイス専用なのである。
このイスに出会ったときに、これを持ち運ぶのに、革ケースが欲しいとまず考えた。
で、試行錯誤の結果この形になったというわけだ。
いい感じにぴったり納まった。
手に持って歩いてもよし。腰にぶら下げて歩いてもよし。
手ぶらでイスが携帯できるなんて、ラーメン屋の行列も怖くないというものだ。
アウトドアの楽しみが一つ増えた。
2014年06月02日
再びプラチナの彫刻機
大層な、ドーム型のカバーに覆われたこの機械。
以前も紹介したペンに名前を入れる手動彫刻機である。
カバーがかかっていた分、とてもきれいな状態で残っていた。
今回の物のほうが少し新しいように見える。
いかにも「機械です」という佇まいがいい。
活字や、彫った文字に色を入れるための金銀のロウもそのままきれいに残っている。
一番最後にこの機械で彫られた名前は、「剛士」というらしい。
銘板には、以前のものと同じく、“PLATINUM INDUSTRY CO., LTD“の社名がある。
プラチナ万萬年筆㈱が一時的に『プラチナ産業㈱』に社名を変えていたのが、昭和22年から37年のことだから、そのあいだの製品ということになるのだろう。
ちなみに以前紹介したものの銘板にも同じ記載があったが、モーターの製作会社名が違っている。
『HANAZUKA ELECTRIC IND.Co.LTD』 だったのが、今回の物は『CORONA MOTOR CO., LTD』になっている。
ただ、モーター自体の名称がどちらも『Corona Engraving Motor』となっているから、この会社もその間に社名変更をしているのだろう。
では、早速試してみよう。
ペンをセットする。
彫る名前の活字を並べる。
これをなぞって彫っていく。
出来上がった文字はほとんど目立たない。
ここに色を埋め込んでいく。
するとクッキリ文字が浮かび上がる。
綺麗にできた。
練習して上手になれば、まだまだどちらも現役で行ける。
2014年05月31日
日本の夏 芝浦製作所の夏
今年も、本格的な夏がやってきたようだ。
狭い書斎は早くも暑苦しい。
そこで、今年も芝浦製作所(SHIBAURA ENGINEERING WORKS)の電氣扇の登場と相成った。
今年のSEWは、ジェニーのようにちょっとご機嫌斜め。
スイッチを入れてもなかなか回らない・・・。
「なんで今頃まで放っておいたのよ!ハートキュンキュン、泣き出しそうよ一人ぼっちは・・・」みたいな。
エアーを吹きかけて、「いいこ、いいこ」と声をかけると、しぶしぶといった感じでゆっくりと回り始めた。
そうすればとにかく少しは気がおさまるのであった。
なんともかわいい、芝浦電氣扇。
2014年05月26日
ドイツAddiator社の計算機
渋い革のケース。
中は、これまた超渋いルックスのカード状の機械。
ドイツで1920年に創業されたAddiator社の、携帯用計算機である。
真鍮の表情がめちゃくちゃかっこいい。
取扱説明書付きなのはいいのだが、ドイツ語はさっぱり分からない。
それでも雰囲気で試してみる。
まず、付属のスタイラスペンで置数する。
次に、各桁で足す数の分だけペンを下にスライドさせていく。
すると、途中ペンが止まって上に赤い↑が出てくることがある。
そうしたら、ペンを逆に上まで持って行って桁を上げる。
そうすると、答えが表示されるというわけだ。
これ、裏面も同じようになっていて、現れる数字は表面とリンクしている。
裏面は引き算用というわけだ。
これで加算と減算を連続して計算することもできるのである。
掛け算、割り算はできない。
多少まどろっこしいが、正確に計算できる、ドイツ版の計算尺といったところだろうか。
ちなみにこれを引き上げると御破算になる。
日本国内で、画期的な一般大衆向け電卓カシオミニが発売されたのが1972年のこと。
それから約10年後、ドイツではAddiator社がその役目を終え廃業する。
栄枯盛衰。
しかし、こんな魅力的な道具が姿を消すというのは、実にさみしいものである。
2014年05月25日
松竹錠
銭湯の下足箱にある木札の錠。
松と竹がデザインされた、その名も『松竹錠』。
何人もの人の手に触れられて艶の出た木札がいい感じ。
ステンシルの番号も渋い。
下に出っ張るつっかえを、この切込みの入った木札が押し開ける仕組み。
札を入れると鍵が開く様子がわかる。

その昔、銭湯には下足番といって、お客の履物を預かる専門の人がいて、このような鍵が必要になったのは戦後になってからのようである。
古い下駄を履いて行って、新しい下駄をちゃっかり履いて帰るような輩が少なからずいたようなので、これは必需品だったと言える。
2年前の第一回東京蚤の市の時に出会った『カナリヤ錠』に相棒ができた。
2014年05月24日
マックスの古いホッチキスHD-10
マックスの古いホッチキス。『HD-10』。
デッドストックのようで、ピカピカ。
箱がいい。
MAX-10からHD-10に品番変更になったのが昭和48年のことだという。
これはいったいいつのころの物なのだろうか?
小窓からグリップ部分の色が覗けるのが超キュート。
針はもちろん10号。
気持ちよく綴じられる。
最新のものはもちろんいいけど、やっぱ古いものは味があるな。
2014年05月23日
純和風のホッチキスNo.1
またまた出会ったホッチキスNo.1。
最近は、見かけると連れて帰らないではいられない感じだ。
純和風調のデザインである。
台座のところには、斧を二つ重ねたようなトレードマークの銘板がある。
では、さっそくムカデ針を入れて試してみよう。
ずっしりと重たい、独特の手応え。
綺麗に留められた。
儀式を終えて、これで仲間入り。
2014年05月22日
イギリスの人気子供番組スーティーショーのシロフォン
これもmenuにて一目ぼれ。
古いティン缶に、色賑やかで楽しげなイラストが描かれている。
この耳の黒いベアは、“スーティー”というイギリスの人気キャラクター。
1952年に始まったイギリスの超人気テレビ番組『スーティーショー』のなかで、ハリー・コルベットというおじさんが操るパペットとして登場し、一躍大人気になったのだそうだ。
中を開けると、何と鉄琴が隠れていた。
色鮮やかな金属の鍵盤。
ど・れ・み・ふぁ・そ・ら・し・ど・れ・みの10音階。
たたくと、実にいい音が響く。
内蓋にある楽譜通りにたたくと、聞き覚えのあるメロディ。
スコットランド民謡の『アニーローリー』だ。
「僕にも弾けた!」
楽器はいいなあ。
2014年05月21日
イギリスの古い折りたたみイス
前から目を付けていた、イギリスの古い折りたたみイス。
東京蚤の市の、antiqueshop menuにて。
小さいながらしっかりとしたつくりで、人気のアイテムだそうだ。
もちろん大人が座っても大丈夫。
丈夫でカラフルな布と、インダストリアルで武骨な金具の組み合わせがいい。

折りたたむとこんなにコンパクトに。
専用のケースを作って、腰からぶら下げて歩いたら便利だろうなあ。
ラーメンの行列も怖くない。
っていう。
2014年05月18日
2014年05月16日
壹銭五厘の切手が貼られた古い絵葉書
古い絵葉書。
猿沢の池のようだ。
この葉書の差出人(性別判別できず)は、旅先の大阪湊町の大和屋旅館から、東京市の本郷湯島にいる立石さんに送ったものらしい。
『東京市』は、明治22年から昭和18年まで存在していたという。
京都から奈良を巡り、そして夕方大阪湊町に到着。
今は夕食を済ませ、これから夜景を見物に行くという。
貼られた切手は、壹銭五厘。
残念ながら消印は読み取れないが、この金額でハガキが届いたのは、明治34年4月から。
大正12年4月に二銭に値上がりしているから、そのあいだに送られたものと思われる。
差出人と立石さんは、いったいどんな関係なのだろう。
夫婦?
親子?
兄弟?
親友?
それとも恋人?
そんな想像を掻き立てる、実に味わいのある葉書なのである。
2014年05月15日
携帯用スライド式ルーペ
ちょっと渋い小さなスチールのケース。
ちょうどマッチ箱くらいの感じである。
“Scoper“の刻印。
特許出願中とでも訳すのだろうか。
ケースをスライドさせると、中にはルーペが納まっている。
バネ仕掛けで、「ビヨン」と飛び出す。
持ち運びに便利な、これはスマートなスライド式のルーペである。
イギリスあたりのヴィンテージなのかなあ。
こういうのが便利に感じるというのは、ちょっと複雑なお年頃なのである。
2014年05月11日
コーリン高級硬筆書写用鉛筆 太芯のド迫力
コーリン鉛筆㈱の硬筆書写用鉛筆を発掘した。
No.5800。硬度は4B。太芯。
このコーリンは顔が左を向いているから、1982年以降の比較的新しいやつである。
それ以前のロゴは右向き。
以前紹介したシャープ芯ゴールドの顔は右を向いていた。
「右向きは後ろ向きのイメージでよくないから」と向きを変えたら、その後15年ほどで廃業に至るのは皮肉なことなのだが・・。

さて、肝心の鉛筆はというと。
“太芯”を売り文句にしているだけあって確かに軸の中で芯の占める割合が多い。
削ってみるとその芯の太さが実感できる。
通常サイズの鉛筆と比べたらこの通り、違いは一目瞭然。
“ジャンボ”を名乗る、ステッドラーのジャンボ書き方鉛筆といい勝負である。
ということは、芯の太さは2mm程度ということになる。
硬度2Bのステッドラージャンボに対して、このコーリンは4B。
さすがに迫力が違う。
紙に黒鉛を載せているという感覚だ。
書くことが楽しくなる鉛筆である。
2014年05月06日
役立たずのバネ
錆びついて伸びなくなったバネがある。
それを、機能の上で役立たずとするのか。
それとも、その佇まいの中に美しさを見出すのか。
本来の役目を果たさなくなって本人は不本意であろうが、そこには何にも代えがたい存在感というものが確かにある。
たかが錆びたバネ。
されど、錆びたバネである。
そんなもの達の言葉に耳をすます夜。
2014年04月28日
アメリカのノベルティ 消火栓のシャープペン
ちょっと変わったシャープペン。
アメリカの古いノベルティのようだ。
消火栓のフィギュアがついている。
MUNICIPAL
PIPE & FABRICATING
そして、テキサス州のヒューストンの住所、私書箱や電話番号が刷られている。
シャープメカは繰り出し式。
芯は1.3mmかな。
アメリカにはこの手のノベルティが多かったのだろうか。
こんなのもらったらうれしいだろうな。
2014年04月27日
古いアメリカ製の手回し鉛筆削り
アメリカ製の小ぶりな鉛筆削り。
“THE GEM” は社名なのかブランド名なのか。
MADE BY AUTOMATIC PENCIL SHARPENER CO. CHICAGO U.S.A.とあるから、
シカゴの自動鉛筆削り社製っていうことになるのかなあ。
いずれにしろ、いい雰囲気の鉛筆削りである。
ハンドルのつまみが木っていうのがいい。

刃はシングルタイプ。
トンボのやつと同じだ。
ちなみにBOSTONはダブルである。
古いけれど、よく削れる。
仲間入り。
2014年04月26日
初めての古道具屋にて ミニカー鉛筆削り
初めての古道具屋。
ちょっとドキドキしながら、それ以上にワクワクしながら扉を開ける。
視界に入ってくる色調。
店全体にセピア色のフィルターをかけたような、落ちたトーン。
店主にあいさつし、並んだ古道具をざっと見渡す。
自分の好みに合った古道具屋は、あるようでなかなかない。
しかも地元でそんな店に出会ったときには幸せを感じるのである。
そういう店の主の言葉は、決まって夢であふれている。
そして古道具を譲ってもらうというより、まるで彼の夢を分けていただいているかのような気持ちがするのである。
そんな初めての古道具屋で出会ったこれ。
大事そうにカウンターの奥から出してきてくれた、古いミニカー。
アメ車だろうか。
金属のざっくりとした武骨な雰囲気と、この色に一目ぼれしてしまった。
そして、後ろに空いた穴。
そう!
これ、実は鉛筆削りなのである。
これが、驚くほどよく削れる。
こんなに尖がる鉛筆削りはそうない。
小さく“JAPAN”の刻印。アメリカ買い付けというから、日本製の逆輸入品ということになる。
道理でよく削れるはずだ。
精緻な作りで、刃は直接ボディにネジ留めされている。
ちょっと見たことのない、素敵な逸品である。
2014年04月25日
クラッシッククロックの鉛筆削り
クラシカルな置時計。
裏側は、いくつもの歯車が複雑に絡み合っている。
文字盤の灼けた感じがいい。
という、例によって鉛筆削りである。
裏のつまみを回すと針が回る仕組みが面白い。

針が回るときにカチコチいうのは、このバネが歯車をはじくカラクリによる。
そんな細かい効果音に凝ってるところも、なかなかである。
素敵な逸品。